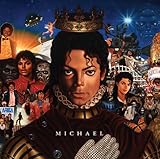Wild horses couldn't drag me awayWild, wild horses, we'll ride them some day"Wild Horses"
今回はThe Rolling Stonesです。僕の音楽人生の中でも大きな位置を占めるバンドですが、ようやくのご紹介です。
WikiPediaではこんな風に紹介されています。
60年代は国により違った形のアルバムがリリースされることが多かったんですね。ややこしいですな。
また自分たちで立ち上げたローリング・ストーンズ・レコードからの初めてリリースされたアルバムでもあります。
まずは簡単なデータから。
発売日
1971年4月23日
最高位
Billboard Pop Albums 1位
UK Top Album 1位
評価
Allmusic 5点
Rolling Stone 5点
関係ない話ですが、ギターを始めてからそれほど経たないうちに、わりと簡単に演奏出来てしまうKiethのオープンG(一番低い音の出る6弦を取り付けず5弦を通常から一音下げたGの音にするというチューニング法、こうするとコードが指一本で弾けてしまうという魔法のような方法です)で練習してしまったというのが、その後のギターの上達の遅さにつながってしまったと言えるでしょう。ラクしちゃいかん、ということですね(いや、まじめに練習しだすとオープンGも奥が深いんですけどね。ただコツをつかむと割と耳コピがし易くなります)。
収録曲
1."Brown Sugar"★★★★★
初めて聴いた時の衝撃は忘れられません。イントロのギターカット。なんでこんなフレーズ思いつくんでしょうか?このノリがStonesなんですよね。いやぁ、かっこいいですね。
2."Sway"★★★★★
ヘビーなギターで始まるミドルテンポのナンバー。このビートに身を委ねていると、ほんとに気持ちがいいです。いつまでも聴いていたい。
3."Wild Horses"★★★★★
アコースティックなバラード。Stonesのバラードって結構ベタな曲が多いと思うんですけど、この曲はサジ加減が絶妙です。大好き。
4."Can't You Hear Me Knocking"★★★★★
荒々しいギターのリフ、そこに飛び込んでくるMickの「Yeah‼」と始まるボーカル。いやあスリリングだわ。ものすごいタイミングだもんなぁ。曲の後半はインプロビゼーション。なんかGeateful Deadみたい。この頃のStonesが持っていた妖しげなオーラがビンビン漂ってきます。
5."You Gotta Move"★★★★☆
古いBluesのカバー。原曲は聴いた事がないんですよね。いつか聴きたいなぁとずっと思ってはいるんですが…。スライドギターに絡みつくMickのボーカルが非常に魅力的です。
6."Bitch"★★★★☆
このリフもかっこいいんだよなぁ。ただ前作に収録されている「Live With Me」にちょっと似てますよね。あとこの曲はギターロックだと思ってたんですが、改めて聴いてみるとホーンがふんだんに使われていて結構にぎやかな曲ですね。
7."I Got the Blues"★★★★★
こんなにいい曲だとは思ってなかったな。メロディ的には60年代のアルバムに収録されていてもおかしくなさそうな感じですが、演奏力が上がってますね。よりソウルフルになり説得力がありますね。すごいな。
8."Sister Morphine"★★★☆☆
この曲ってStonesファンの間ではかなり評価が高い、という印象があります。Liveで演奏して欲しい曲アンケートとかでも入っていた記憶があるし。でも、いまいち良さがわかんないんですよね。もう少し聴き込む必要があるのかなぁ。
9."Dead Flowers"★★★★★
高校の文化祭オーディションの時この曲演ったんです。懐かしいな。アコースティックの軽快なロックっていうイメージだったんですけど、カントリー色が強いんですね。
10."Moonlight Mile"★★★★☆
ちょっと東洋風なメロディですね。ELOぽい感じもするな。混沌の中から美しいメロディーが立ち上がってくる感じでいいですねぇ。
総合評価 ★★★★★
改めて聴いてみると、思ってた以上に高評価な曲が多かったですね。特に4曲目までの流れは完璧。捨て曲なしの大名盤です。このアルバムは自身のレーベルを立ち上げて最初のアルバムということもあり、60年代のアルバムとこのアルバムからの流れにちょっとうまく繋がらないような印象もありました。今回改めて聴いてみると、前作"Let It Bleed"で顔を出したカントリー風味がうまく昇華され彼ら独自の音楽を作り上げているんだな、と感じようやく繋がりが実感できました。
・アーティスト紹介
60年代から第1線で活躍するモンスターバンドです。Rockといえばこのバンド。こう考える人も多数いらっしゃるのではないでしょうか?時代の流れにも敏感でその都度スタイルを変えたアルバムを発表していますが、どのアルバムもStonesの音楽として響いているというところが、このバンドの強さだと思います。WikiPediaではこんな風に紹介されています。
ザ・ローリング・ストーンズ (The Rolling Stones) は、1963年にレコードデビューした、イギリス ロンドンのロックバンド。ロック草創期の1960年代前半から現在まで半世紀近く、1度も解散することなく第一線で創作を続ける、ロックの代名詞的な存在である。エアロスミスやガンズ・アンド・ローゼズ、オアシスなど、ローリング・ストーンズを崇拝するアーティストは数知れない。略称ストーンズ。
・どんなアルバム?
Sticky FingersはThe Rolling Stonesのイギリスでの9枚目、アメリカでの11枚目のアルバムです。60年代は国により違った形のアルバムがリリースされることが多かったんですね。ややこしいですな。
また自分たちで立ち上げたローリング・ストーンズ・レコードからの初めてリリースされたアルバムでもあります。
まずは簡単なデータから。
発売日
1971年4月23日
最高位
Billboard Pop Albums 1位
UK Top Album 1位
評価
Allmusic 5点
Rolling Stone 5点
・このアルバムの思い出
高校生の頃、バンドでStonesのカバーをやっていたという話は以前書きました。最初の頃に練習していた曲がこのアルバムの1曲目「Brown Sugar」と「Dead Flowers」でした。という訳で結構思い入れのある曲が入っているわけなんですが、ちゃんと聴いたのは社会人になってからかもしれません。当時はお金がなかったんでベストアルバムしか聴いてなかったんですね。関係ない話ですが、ギターを始めてからそれほど経たないうちに、わりと簡単に演奏出来てしまうKiethのオープンG(一番低い音の出る6弦を取り付けず5弦を通常から一音下げたGの音にするというチューニング法、こうするとコードが指一本で弾けてしまうという魔法のような方法です)で練習してしまったというのが、その後のギターの上達の遅さにつながってしまったと言えるでしょう。ラクしちゃいかん、ということですね(いや、まじめに練習しだすとオープンGも奥が深いんですけどね。ただコツをつかむと割と耳コピがし易くなります)。
・アルバムレビュー
Stonesの代表的作品というばかりでなく、Rock史に残る名盤として評価が定着しております。また、発売当初は物議を醸したらしいアルバムジャケットも他を寄せ付けないほどのかっこよさ。よくぞこんなデザインを思いつけるもんですよね。才能があるっていいよなぁ。それでは聴いていきましょう。収録曲
1."Brown Sugar"★★★★★
初めて聴いた時の衝撃は忘れられません。イントロのギターカット。なんでこんなフレーズ思いつくんでしょうか?このノリがStonesなんですよね。いやぁ、かっこいいですね。
2."Sway"★★★★★
ヘビーなギターで始まるミドルテンポのナンバー。このビートに身を委ねていると、ほんとに気持ちがいいです。いつまでも聴いていたい。
3."Wild Horses"★★★★★
アコースティックなバラード。Stonesのバラードって結構ベタな曲が多いと思うんですけど、この曲はサジ加減が絶妙です。大好き。
4."Can't You Hear Me Knocking"★★★★★
荒々しいギターのリフ、そこに飛び込んでくるMickの「Yeah‼」と始まるボーカル。いやあスリリングだわ。ものすごいタイミングだもんなぁ。曲の後半はインプロビゼーション。なんかGeateful Deadみたい。この頃のStonesが持っていた妖しげなオーラがビンビン漂ってきます。
5."You Gotta Move"★★★★☆
古いBluesのカバー。原曲は聴いた事がないんですよね。いつか聴きたいなぁとずっと思ってはいるんですが…。スライドギターに絡みつくMickのボーカルが非常に魅力的です。
6."Bitch"★★★★☆
このリフもかっこいいんだよなぁ。ただ前作に収録されている「Live With Me」にちょっと似てますよね。あとこの曲はギターロックだと思ってたんですが、改めて聴いてみるとホーンがふんだんに使われていて結構にぎやかな曲ですね。
7."I Got the Blues"★★★★★
こんなにいい曲だとは思ってなかったな。メロディ的には60年代のアルバムに収録されていてもおかしくなさそうな感じですが、演奏力が上がってますね。よりソウルフルになり説得力がありますね。すごいな。
8."Sister Morphine"★★★☆☆
この曲ってStonesファンの間ではかなり評価が高い、という印象があります。Liveで演奏して欲しい曲アンケートとかでも入っていた記憶があるし。でも、いまいち良さがわかんないんですよね。もう少し聴き込む必要があるのかなぁ。
9."Dead Flowers"★★★★★
高校の文化祭オーディションの時この曲演ったんです。懐かしいな。アコースティックの軽快なロックっていうイメージだったんですけど、カントリー色が強いんですね。
10."Moonlight Mile"★★★★☆
ちょっと東洋風なメロディですね。ELOぽい感じもするな。混沌の中から美しいメロディーが立ち上がってくる感じでいいですねぇ。
総合評価 ★★★★★
改めて聴いてみると、思ってた以上に高評価な曲が多かったですね。特に4曲目までの流れは完璧。捨て曲なしの大名盤です。このアルバムは自身のレーベルを立ち上げて最初のアルバムということもあり、60年代のアルバムとこのアルバムからの流れにちょっとうまく繋がらないような印象もありました。今回改めて聴いてみると、前作"Let It Bleed"で顔を出したカントリー風味がうまく昇華され彼ら独自の音楽を作り上げているんだな、と感じようやく繋がりが実感できました。